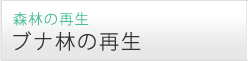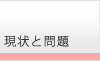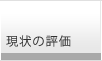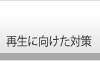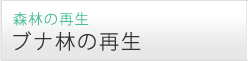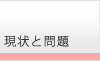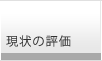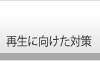丹沢大山地域における現状と問題
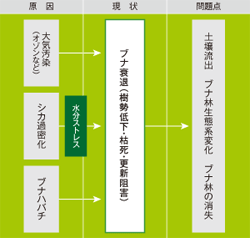
ブナの要因連関図
現在、丹沢山地の主稜線一帯ではブナをはじめとした高木(以下、ブナ林)の衰弱・枯死が進行しています。その原因はオゾンなど大気汚染の影響、ブナの葉だけを食べるブナハバチの大発生、温暖化、少雪化、林床植生の退行、土壌乾燥化などによる水分ストレスなどが複合的に関係すると考えられます。主稜線部の南から南西斜面ではブナ林が衰弱し、ササ原になったところもあります。森林消失に至らないところでも、弱ったブナに対してブナハバチの大発生が繰り返されると、ブナが枯死してしまいます。また、このような場所では過密化したシカが稚樹を食べてしまうため、ブナの更新が行われず、将来、ブナを欠いた森林に変容する可能性があります。ブナ林の消失や構造の変化は、ブナに依存するネズミ類やツキノワグマをはじめとしたさまざまな生きものにも影響を及ぼします。
ブナ林の衰退
調査によりブナ林の衰退は丹沢山地のブナ林全体に認められましたが、地区により進行状況が異なっていました。現在、衰弱・枯死が激しいのは鍋割山、塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳など、東丹沢から丹沢中央の主稜線部にかけてです。一方、衰退が少ないのは、西丹沢の大室山、城ヶ尾峠、菰釣山にかけてや、東丹沢の丹沢三峰山稜や堂平です。西丹沢の菰釣山では1980年代にブナやモミの立ち枯れが観察されていますが、最近では衰退がほとんど見られません。
ブナとオゾン濃度
ブナはオゾンへの感受性が高く、高濃度のオゾンにより成長が阻害されたり生理的な機能が低下します。丹沢山地の檜洞丸では、植物成長期間(5月から9月)に、高濃度のオゾンが記録されることがわかりました。特に、卓越風が強く当たる南から南西方向の斜面では、オゾンや風の影響が強く、衰退との関連性が指摘されています。
植生保護柵の設置
神奈川県では、丹沢大山保全対策事業の一環として1997年度から林床植生の衰退の著しい特別保護地区を中心に、植生保護柵を設置しています。植生保護柵内では、植物が繁茂してシカの採食により絶滅が危惧されていた希少植物の回復や、ブナの天然更新に役立っています。